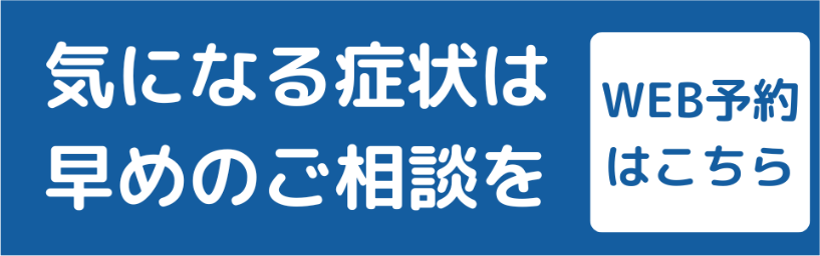1. はじめに

「最近、膝が腫れてるみたい…」 「膝が痛くて曲げ伸ばしが辛い…」
もしかしたら、それは膝に水がたまっているサインかもしれません。
膝に水がたまる(膝関節水腫)と、痛みや腫れ、動きにくさなどの症状が現れ、日常生活に支障をきたすことがあります。
今回は、膝に水がたまる原因や症状、治療法、予防法などを整形外科専門医がわかりやすく解説します。
2. 膝に水がたまる(膝関節水腫)とは?
膝関節は、大腿骨、脛骨、膝蓋骨(お皿)の3つの骨で構成されており、これらの骨の表面は軟骨で覆われています。 軟骨は、関節の動きを滑らかにし、衝撃を吸収する役割を担っています。
また、膝関節内には関節液と呼ばれる液体があり、軟骨に栄養を供給したり、関節の摩擦を軽減したりする働きがあります。
通常、関節液は適切な量に保たれていますが、何らかの原因で過剰に分泌されると、膝に水がたまった状態になります。
3. 膝に水がたまる原因
膝に水がたまる原因は様々ですが、主なものとしては以下のものが挙げられます。
怪我(外傷)
○ 転倒やスポーツなどで膝を捻挫したり、打撲したりすると、関節内部で炎症が起こり、関節液が過剰に分泌されることがあります。
変形性膝関節症
○ 加齢や過度の負担により、膝関節の軟骨がすり減り、炎症が起こることがあります。
関節リウマチ
○ 自己免疫疾患の一種で、関節を包む滑膜が炎症を起こし、関節液が過剰に分泌されることがあります。
感染症
○ 細菌感染により、膝関節内に炎症が起こり、関節液が過剰に分泌されることがあります。
その他の病気
○ 痛風、偽痛風、半月板損傷、靭帯損傷などが原因で、膝に水がたまることもあります。
4. 膝に水がたまる症状
膝に水がたまると、以下のような症状が現れます。
膝の腫れ
○ 膝全体が腫れたように膨らみ、触るとブヨブヨとした感触があります。
○ 特に、膝のお皿の周りが腫れやすいです。
膝の痛み
○ 膝を曲げ伸ばししたり、歩いたりする際に痛みを感じます。
○ 痛みは、運動時だけでなく、安静時にも続くことがあります。
○ 階段の昇り降りや、立ち上がり、しゃがみ込み動作などで痛みを感じることが多いです。
膝の動きにくさ
○ 膝が腫れて動きにくくなり、正座や階段の昇り降りが困難になることがあります。
○ 膝が重く感じたり、引っかかるような感じがしたりすることもあります。
熱感
○ 膝が熱っぽく感じることがあります。
○ 炎症が起きていると、膝が赤く腫れることもあります。
5. 膝に水がたまる検査・診断
膝に水がたまる原因を特定するために、以下の検査が行われます。
問診
○ 症状や既往歴、怪我の有無などを詳しくお伺いします。
○ いつから症状が現れたのか、どのような時に痛みを感じるのかなど、具体的な情報を教えてください。
視診・触診
○ 膝の状態を目で確認したり、触ったりして、腫れや痛みの程度を調べます。
○ 膝の可動域や、不安定感なども確認します。
レントゲン検査
○ 膝の骨や関節の状態を確認します。
○ 変形性膝関節症の進行度合いや、骨折の有無などを確認できます。
MRI検査
○ レントゲン検査ではわからない軟骨や靭帯の状態を詳しく調べます。
○ 半月板損傷や靭帯損傷の有無などを確認できます。
関節液検査
○ 注射器で膝関節内の水を抜き取り、その成分を調べます。
○ 細菌感染や炎症の有無などを確認できます。
○ 採取した関節液の色や粘度、細胞数などを調べます。
6. 膝に水がたまる治療法
膝に水がたまる治療法は、原因や症状の程度によって異なりますが、主なものとしては以下のものが挙げられます。
保存療法
○ 炎症を抑えるために、安静、冷却、圧迫などを行います。
○ 痛み止めや湿布などの薬物療法を行うこともあります。
○ 症状が軽い場合は、サポーターやテーピングで膝を固定することもあります。
○ ヒアルロン酸注射やステロイド注射を行うこともあります。
関節液除去
○ 注射器で膝関節内の水を抜き取り、症状を緩和します。
○ ただし、関節液を抜き取っても、原因となっている病気が治らなければ、再び水がたまる可能性があります。
薬物療法
○ 炎症を抑えるために、ステロイド薬やヒアルロン酸注射などを行うことがあります。
○ 関節リウマチの場合は、免疫抑制剤を使用することもあります。
手術療法
○ 保存療法で症状が改善しない場合や、重度の変形性膝関節症、半月板損傷、靭帯損傷などがある場合は、手術が必要になることがあります。
○ 手術の種類は、関節鏡手術、人工関節置換術などがあります。
7. 膝に水がたまる予防と日常生活での注意点
膝に水がたまるのを予防するためには、以下の点に注意することが大切です。
適度な運動
○ 膝に負担をかけすぎないように、ウォーキングや水泳などの軽い運動を心がけましょう。
○ 運動前には、ストレッチなどで体を温めることが大切です。
体重管理
○ 肥満は膝関節に負担をかけるため、適切な体重を維持しましょう。
○ バランスの取れた食事を心がけ、過食を避けましょう。
姿勢
○ 正しい姿勢を保ち、猫背にならないようにしましょう。
○ 長時間同じ姿勢でいることは避け、こまめに休憩をとりましょう。
ストレッチ
○ 膝関節周囲の筋肉を柔らかく保つために、ストレッチを регулярноに行いましょう。
○ 特に、太ももの筋肉やふくらはぎの筋肉を柔らかくすることが大切です。
日常生活での注意
○ 長時間立ち続けたり、重い荷物を持ったりするのを避けましょう。
○ 膝に痛みを感じたら、無理せず早めに休息しましょう。
○ 階段の昇り降りは、膝に負担がかかりやすいので、ゆっくりと行いましょう。
○ 靴は、クッション性があり、安定したものを履きましょう。
8. まとめ
膝に水がたまる原因は様々ですが、放置すると症状が悪化し、日常生活に支障をきたすことがあります。
「もしかして、膝に水がたまっているのかも…」
と思ったら、自己判断せずに、早めに整形外科を受診しましょう。
適切な検査と治療を受けることで、症状を改善し、快適な生活を送ることができます。
山本整形外科では、膝の痛みや腫れでお悩みの方の診察・治療を行っております。 お気軽にご相談ください。
膝の痛みの症状がある患者様の来院マップ

当院は大阪市東成区に位置しておりますが、区境に位置しているため、生野区、天王寺区からも膝に水がたまる症状のある患者様に来院いただいております。
鶴橋駅から徒歩3分、玉造駅から徒歩10分と電車でのアクセスも良好でございます。
また今里駅や桃谷駅からも徒歩でご来院いただけます。
平日は夜19時まで診察しており、時間予約にも対応しているため、お仕事や学校帰りの方でもご来院しやすくなっております。
膝に水がたまる症状でお悩みの方はお気軽にご相談ください。